|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
| 参考人のメンバー(左から山内、待鳥、富田、今村の各氏)=6月2日、国会内 |
修正内容は、野党共同提案の道運法改正案については、法案の内容となっている参入・増車規制の強化、運賃認可基準の見直しなどの内容を活性化法案の修正や道運法附則の改正として盛り込み、検討条項として措置することとし、活性化法案については、前記内容を含めた野党案の内容を政府案に取り入れて修正することとなりました。この結果、修正案が全会一致で10日委員会、11日本会議で可決され、参議院に送られる見通しとなりました。
よりよい方向で審議を
参考人が議員質問に答弁
衆議院国土交通委員会は6月2日、参考人を招いてタクシー活性化法案、道運法改正案について政府案と4野党共同案の一括審議を行いました。
審議には、参考人として、今村天次書記長が自交総連の代表として初めて招致されたのをはじめ、山内弘隆一橋大大学院教授、待鳥康博全自交書記長、富田昌孝全タク連会長が出席して意見を述べ、議員の質問に答えました(2面に関連記事)。
議員からの質問では、規制緩和後の供給過剰問題や弊害などについて問われ、「2000年の審議で当時の運輸大臣は規制緩和でバラ色になるといった。結果は明白だ。政策の誤りについては真摯な反省が必要と思うがどうか。政府案と野党案どちらがいいのか率直にうかがいたい」(共産・穀田恵二)との問いに、今村書記長は「我々も諸外国の例をあげて成功例はないといったが、間違った規制緩和がごり押しされた。政府案プラス4野党共同案となるのが一番いい。すべてがなしということではなく、よりよい方向で審議してほしい」と回答しました。
| 条 項 | 野党共同案の内容 | 修正協議の結果 | |
| 1.道路運送法改正案 | |||
| (1) | 参 入 6条 |
参入許可条件に、当該事業の開始が営業区域の輸送需要に対し適切なものであるかどうかを考慮して審査することを加える | 活性化法案の検討条項として措置 |
| (2) | 増 車 15条 |
増車の届出制を認可制にする | 活性化法案の検討条項として措置 |
| (3) | 運 賃 9条の3 |
運賃・料金認可基準について、“適正なものを超えないもの”となっているのを“適正なもの”とする | 道運法の原始附則に読み替え規定を措置=附則に「当分の間、『加えたものを超えないもの』とあるのは、『加えたもの』とする」との規定を加える |
| (4) | 事故報告 29条 |
事故報告の対象範囲を拡大する | 活性化法案の検討条項として措置 |
| (5) | 休 廃 止 39条 |
事業の休廃止を届出制から許可制にする | 活性化法案の検討条項として措置 |
| (6) | 登 録 制 (附則) |
改正法案の附則で、運転者の資格・登録制度のあり方の検討を明記し、対象地域の全国拡大などの検討を行うようにする | 活性化法案の検討条項として措置 |
| 2.タクシー活性化法案 | |||
| (1) | 目的規定 1条 |
適正化及び活性化を推進することを目的とする | 修正)地域の交通の健全な発達に寄与することを明示する |
| (2) | 地域指定 3条 |
都道府県知事、市町村長が特定地域を指定するよう要請できるようにする | 第4項、第5項を新設)都道府県知事・市町村長が指定を要請できるようにする |
| (3) | 都市計画 との調和 9条 |
− | 第3項を新設)地域計画は都市計画等との調和が保たれなければならないものとする |
| (4) | 減・休車 11条3項 |
供給輸送力減少措置として減車・休車を含むことを明示する | 国土交通省令に措置)減車・休車を供給輸送力の減少の措置として省令で明示する |
| (5) | 特例廃止 15条 |
道運法改正で増車を全国で認可制にするので、特定地域のみの認可制は廃止する | 検討条項として措置 |
| (6) | 資金確保 16条 |
特定事業推進のための資金確保に加え、融通・あっせんを加える | 修正)国による資金の「融通、あっせんその他の援助」の規定を追加 |
誇りと働きがい回復させる施策を
増車抑制の対策強化を要請
国土交通委参考人質疑
今村書記長の意見陳述(要旨)
 |
| 参考人として意見を述べる今村書記長 |
本委員会で審議されている規制緩和実施後に発生した諸矛盾の解消とタクシー規制のあり方に関わる問題については、多くのタクシー労働者とその家族が深い関心と期待を持って審議動向に注目しています。
とくに、規制緩和実施後に発生した増車・運賃競争はタクシー労働者にとっては、死活的問題であり、“多すぎるタクシーを減らせ、増車はするな、バラバラ運賃反対”は、みんなの切実な要求となっています。
タクシーサービスの安全性と快適性の確保は、何よりもタクシー運転者の自覚と努力なしには実現しません。
少なくとも現状の低賃金、長時間労働の構造を放置したままでは、タクシーの安全性や快適性の基礎は不安定なものといわざるを得ないのです。そもそも、そのような不合理なタクシーシステムでは成熟した社会の「社会資本」としての内実をもたないし、公共交通機関としてタクシーを処遇しているともいえません。
タクシー労働者の労働条件の改善は、タクシー運転者がタクシーの公共性を自覚し、それにふさわしいタクシーサービスの提供に努力する基盤をつくることになります。タクシー労働者に社会的水準の労働条件を保障すること、それへの接近のスピードを上げるために必要な施策を断行することが求められます。
国・行政には、規制緩和後、タクシー車両が増加し需給の不均衡が拡大した結果、賃金の大幅な減少や運転者の高齢化といった労働環境の悪化がもたらされていることへの責任があり、タクシー輸送の安心・安全と働く労働者の職業に対する誇りと働きがいを回復させる施策を実行する適切な対応が急務です。
その根幹を成すのが」需給調整機能の確保と適正運賃の問題です。
タクシー適正化特別法案は、「タクシーの機能を維持、活性化するために現時点で必要と考えられる対策」として位置づけられていますが、その緊急性と実効性確保の観点から、4野党共同法案における修正部分の積極的受け入れのもとに与野党一致での成立をめざしていただきたい。その場合、法案に盛り込まれている減車に関わる枠組み及び新規参入と増車抑制の実効性をより確かなものとする方向での対策強化を要請するものです。
タクシーの特性からして、規制緩和を実行した世界の主要都市が抱えた矛盾は、結局のところ需給調整機能と適正な運賃の確保の問題であることを考えれば、答えは明らかです。
この間題において、4野党共同提案の道路運送法一部改正は、タクシーのあるべき将来像との関係において、特別の重みを持つものと考えます。賛成か反対かという選択ではなく、十分な検討を要請するものです。
安全運転では生活保護に届かず
各地方で運送収入が大きく低下
安全運転実態調査結果
この調査は、労働時間を守って安全運転で働いた場合の運送収入と通常営業とを比較することで、普段の働き方がどの程度加重になっているかを確かめるものです。
今年の調査では福岡を除き各地方とも運収が大きく低下しています。5地方平均ではテスト車の運収が前年比8%減の2万9015円、通常営業が同14%減の3万0740円でした。両者の差は1726円、通常営業はテスト車の6%増しです。多い部分は、残業したり休憩時間を削るなどの無理をして増やしているということになります。実車率はテスト車34・2%、通常営業35・7%で、ともに過去最低でした。
テスト車の数値から安全運転で得られる年収を推計すると、賃率60%で計算してもすべての地方が生活保護基準にも届かないということになります。安全運転では到底くらせないという結果です。
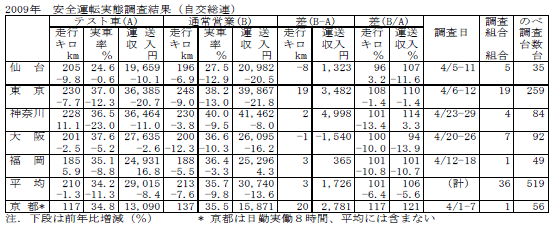
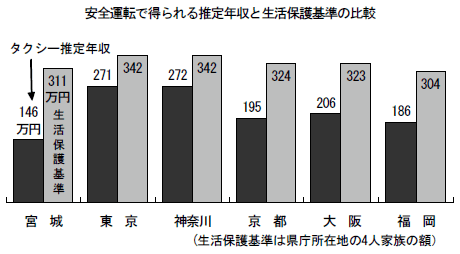
乗務員からは嘆きの声
鹿児島、長崎で宣伝行動
 |
| NHKが取材する中乗務員から聞き取り調査をする鹿児島地連の仲間=5月18日 |
【鹿児島】鹿児島地連は九州ブロックの宣伝カーを使い5月18日から22日まで、本部の宣伝ビラの裏に独自のビラも作成し、宣伝行動を行いました。
福岡地連の内田事務局次長もかけつけ、のべ21人が参加し、対話と聞き取り調査を行いました。
10万円〜15万円の給料しかもらえないと嘆きの声が聞かれ、中には「営業収入40万円くらい。2時間くらいしか寝てない」など、非常に厳しい状況にあります。
隔勤では学校に行かせられない
 |
| 宣伝カーから訴える長崎地連の仲間 |
【長崎】長崎地連は、5月29日〜6月2日、宣伝行動を行い、ビラ、自交総連新聞など200枚を配布し、16人が参加しました。
5月29日の佐世保では、辻待ちでは1時間に1回で、運がよくて2回。「隔日勤務では、子供は学校に行かせられない」との声が聞かれました。
6月2日の長崎市内と大村駅・長崎空港では、「客待ちでは2時間は最低かかるし、下手すれば朝から並んで昼までに1回も実車できない」と言っていました。
北の核実験に強く抗議
平和な世界をアピール
平和大行進 静岡
 |
| のぼりを掲げ行進する静岡地連の仲間=5月29日、浜松市内 |
途中5月25日、焼津市のビキニ水爆実験の犠牲者久保山愛吉さんの墓前で、北朝鮮の核実験強行の報道を聞いた静岡県平和行進団は、核計画の即時中止と6か国協議への復帰を求める抗議声明文を、満身の怒りを込めて表明しました。
核兵器廃絶を実現させるために大きく動き始めた中で強行された北朝鮮の核実験は、世界の核兵器廃絶の努力に逆行するものであり、その行為は断じて許すことはできません。
一行は5月29日に、浜松市東区の静岡地連事務所近くにさしかかり、地連からも一緒に参加して核兵器の廃絶を訴えながら行進し、核兵器も戦争もない平和な世界の願いをアピールしました。
第一交通産業との8年2か月に及ぶ闘争終結に対する「声明」(要旨)
2009年6月2日 自交総連大阪地連
争議が始まってからこの間、100件に近い係争事件の「判決」「命令」が出たものについては、組合が勝利を続け、第一交通を追い込んだ。
なかでも、究極の組合つぶしといえる佐野第一交通の偽装解散・組合員55人全員解雇事件では、2006年10月26日大阪高裁は、組合側が主張した「法人格否認の法理」で第一交通を断罪した。そして、黒土始会長、田中亮一郎社長ら個人に対しても共同不法行為を認定し、さらに組合つぶしによる損害(組合員減)を上部団体の大阪地連にも認めるなど、画期的内容の「判決」を組合は勝ち取り、最高裁も2008年5月1日、追認する判断を下した。
自交総連本部をはじめ、全労連、大阪労連、大阪争議団共闘、そして組合を支え続けた大阪地連加盟各単組の下支えがあればこその結果である。大阪地連は今後も、同闘争に見られた組織攻撃には、断固として闘っていく。ご支援いただいた各団体、各人に対して心からの感謝を申し上げ、第一交通闘争の勝利的和解を宣言する。
| 新加盟のなかま | (764)北海道・自交総連朝日交通労組 |
不当労働行為と闘う |
【北海道】札幌市にある朝日交通で働く仲間は5月20日、自交総連朝日交通労働組合(黒川恵二委員長、4人)を結成、自交総連に加盟しました。
会社にはユニオンショップがありましたが、方針の違いから、黒川さんが一人で脱退し、個人加盟のハイタクユニオンに加盟。その後3人の仲間が結集したことから単組を立ち上げました。
加盟後は、会社の不当労働行為とは闘う決意です。