|
|
 |
| 新年度運動方針案、予算案を確認した第4回中執=9月5日、東京・入谷区民館根岸分館 |
会議では、既に原案を提起している運動方針案(本紙9月1日付)について最終確認したうえ、方針の基本理念として「たたかう労働組合の役割を発揮し、まともな労働条件の確立、組織の強化拡大」のスローガン案を確認しました。
予算案に関しては、各地方からの登録減が1400人を超え、年間予算で1000万円を超える大幅な減額となることから、次年度の専従役員定数の1人減員をはじめ各項目で大幅な縮減をせざるを得ないことになりました。自交総連の運動にも影響するため、各地方での組織拡大によって早急に登録人員、財政基盤の回復を図ることを合わせて確認。組織の強化拡大がまったなしの課題となっていることが議論の中でも強調されました。
第35回定期大会は10月16、17日に東京・全労連会館で開催します。
秋から来春闘にかけての闘争方針(3面参照)を決定し、ただちに実践していくことになりました。
有期雇用は5年で無期転換
65歳までの継続雇用義務化
労働契約法・高齢者雇用安定法改正
9月8日に閉会した通常国会で労働契約法(有期雇用法制)と高年齢者雇用安定法の改正が成立しました。有期雇用の規制
【解説】労働契約法改正は、1年とか半年とか期間を定めた有期雇用を制限するものです。そもそも、安上がりで解雇しやすいという目的のために雇用期間を有期にするという雇い方自体がおかしいわけですが、そこを規制する規定は入りませんでした。5年で無期雇用に転換となりますが、直前での雇止め、空白期間を利用した無期転換逃れがされるおそれがあります。
継続雇用の義務化
高年齢者雇用安定法は、年金の支給開始年齢に合わせて、原則として希望者全員の継続雇用を企業に義務付けるものです。経過期間終了後は、労使協定があっても選別は許されなくなります。ただし例外的な措置が修正で追加され、健康状態や解雇に相当するよう著しい問題がある労働者は排除できるとされました。その基準が恣意的に悪用される可能性があります。
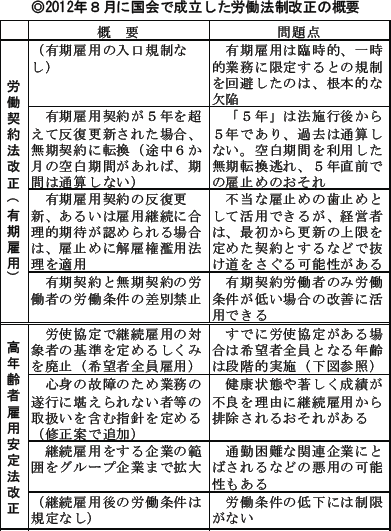
142の特定地域を再指定へ
国土交通省 タクシー活性化法
労働条件の改善まだ不十分
国土交通省は9月7日、9月末で指定期限をむかえるタクシー活性化法の特定地域を10月以降も原則としてすべて再指定することを明らかにしました。 活性化法では供給過剰の地域が指定地域とされ、運転者の労働条件改善のための減車計画等が地域協議会で決められました。国交省では、09年の指定から3年が経過し、減車等により日車営収が改善されるなどの効果があったが、各地域の指標を見ると、依然として指定要件に合致しているため再指定するとしています。
つまり、一定の減車はすすんだが、まだ十分な労働条件改善には至っていないので、ひきつづき改善をめざして再指定するということです。
今回再指定されるのは142地域、09年以降追加指定されてまだ3年の期限がきていない地域は15地域あります。
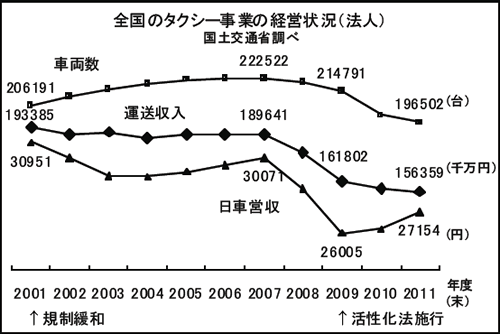
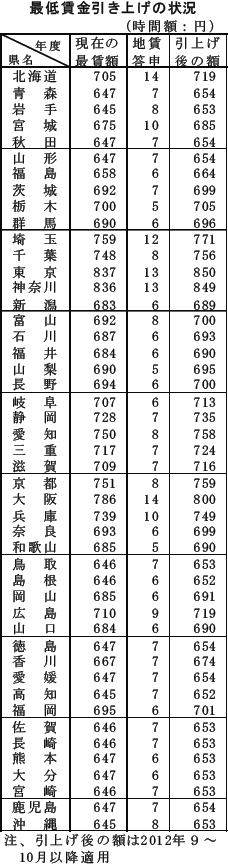 最賃5〜14円引上げ
最賃5〜14円引上げ
引上げ答申出そろう
地方最低賃金審議会
今年度の最低賃金引上げについての地方最低賃金審議会の答申が出そろいました。中央最低賃金審議会での引上げ目安は、生活保護との逆転地域を除き4円と低額でしたが、地方で一定の上乗せがされて5〜14円の引き上げとなりました。 引上げ後の最高は東京の850円で、最低は島根・高知の652円です。引上げ額では北海道・大阪の14円が最高で、栃木・山梨・和歌山の5円が最低でした。
新しい最低賃金額は、地方ごとに開始日が異なり、9〜10月以降適用となります。
空白県なくす運動強化
争議支援など方針決める
関東ブロック第34回総会
 |
| 新年度方針などを話し合った関東ブロック総会=9月5日、東京・自交共済事務所 |
2011年度運動総括では、昨年、静岡で開催した第33回総会から東京地連が中心となってとりくまれた関東運輸局請願行動、タクシー活性化法や6地方でおこなった宣伝行動についての報告がされました。また、次年度の運動方針では、引き続き関東ブロック内での空白県をなくすためのとりくみ強化や争議組合への支援などを決めました。次年度の役員は、議長に川崎一則(東京)、副議長に黒田謙一(神奈川)、事務局長に吉田貴一(埼玉)各氏、その他幹事が選出されました。
バス労働者にビラ配布で成果
大曲花火大会で宣伝行動
宮城地連
 |
| 新年度方針などを話し合った関東ブロック総会=9月5日、東京・自交共済事務所 |
気温は32度で、チラシ配布にはきびしい状況でした。暑さでドアを閉めているバスに一台一台開けてもらいながらの配布でしたが、どのドライバーも気持ちよく受け取ってくれ、二組で250枚配布することができました。「ごくろうさま、がんばってください」「もう一枚ください」などの激励もあいつぎ、さっそくチラシに目を通してくれました。
今回の宣伝行動では、「自交労働者新聞」の申込書も配布しましたが、さっそく岩手県のバス労働者から申し込みがありました。
1万人を目標に加入促進図る
給付内容を改善し魅力増も検討
自交共済 第31回総会
自交共済は9月6日、東京・台東区入谷区民館根岸分館で第31回総会をひらき、11地方29人が参加して、第30期(2012年度)活動計画を決めました。 自交共済の加入状況は18地方6228人(5月末現在)で、前期より517人減となっています。新規加入は5組合(茨城・東京・大阪・鹿児島)で脱退は3組合(東京・大阪・兵庫)でした。
総会では、共済の魅力を増すため祝金などを重点に給付内容を改善していくことを今後、議論していくこととし、1万人をめざして加入促進をはかっていくことしました。
全労済全国組織事業本部の田所主査が全労済の事業について説明しました。
自交共済は組合員の助け合いとして組合ごとに加入できます。資料は本部にありますので、請求してもらえれば送ります。
自交総連の基本政策
住民の交通権守り労働者の生活も改善
(3)地方政策、国民の交通権の確立を
 |
| 山形・鶴岡市藤島地区で08年から運行を開始した乗合デマンドタクシー。自交総連の自主経営会社ハイヤーセンターが市から委託を受け運行している |
それまで「6項目政策提言」などで、参入と運賃の規制、民主的な運賃決定など全国共通の政策を提言してきましたが、地方では、住民の交通権(移動する権利)が脅かされる事態がすすんでいたことなどから、タクシーを積極的に活用して、交通権を確保し、タクシー労働者の労働条件も向上させるための政策を提起しました。
すでに実現したものもあります。
福祉タクシー・乗合タクシーは多くの自治体に普及、自交総連の組合も運行に積極的な役割を果たしています。内容充実と国による制度化が課題です。
代行運転は新法で二種免義務付けなど規制ができました。
交通政策の協議会は、活性化法で設置され減車を含めて協議されています。
最高乗務距離の規制は、指定地域が拡大され、日勤に対する規制が新設されました。
地方都市・郡部におけるタクシーのあり方についての提言
- 福祉タクシー制度の全国的な確立、改善
身障者・高齢者・患者などのタクシー利用に補助を行う福祉タクシー制度を全国的に確立し、福祉施設の送迎等にタクシーを活用する。
- 乗合タクシーの活用など住民の交通権の確保
乗合タクシーの導入・利便性拡大をはかる。自家用車での送迎など危険な輸送方法は排除し、公的な運転業務にタクシーを活用する。
- 地方都市交通効率化のためのタクシーの活用
自家用車の無制限な増加を抑制し、公共交通機関優先の原則を確立するため、自動車の総量規制などを検討し、タクシー活用策を講じる。
- 地方交通政策確立のための委員会等の設置
地方の総合的な交通政策を協議するために、労働組合を含めた自治体、運輸行政当局、事業者、住民からなる委員会・協議会等を設ける。
- 運転代行の違法行為根絶、規制強化
運転代行の違法行為を根絶するために、タクシー類似の表示灯の禁止、専用車両(2シーター)の義務付けなど取り締まりを強化する。
- タクシーの特性を生かしたサービスの充実
タクシーの特性を生かし、運行の効率化、観光サービス等の充実をすすめる。中小零細事業者の共同・協業化の促進のための支援を行う。
- 実効ある減車措置、最低労働条件の確保
(1)実効ある減車措置。(2)改善基準告示の日勤と隔勤との格差縮小、特例廃止。(3)乗務距離の最高限度は指定地域を拡大し、拘束時間に合わせて規制する。