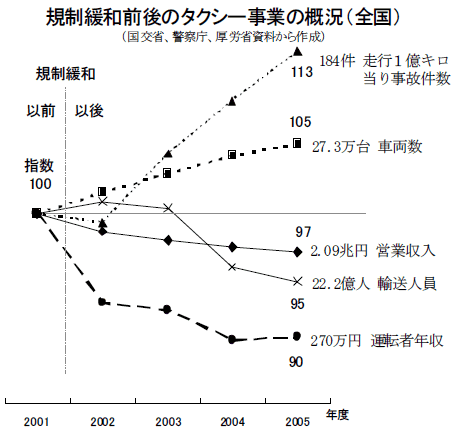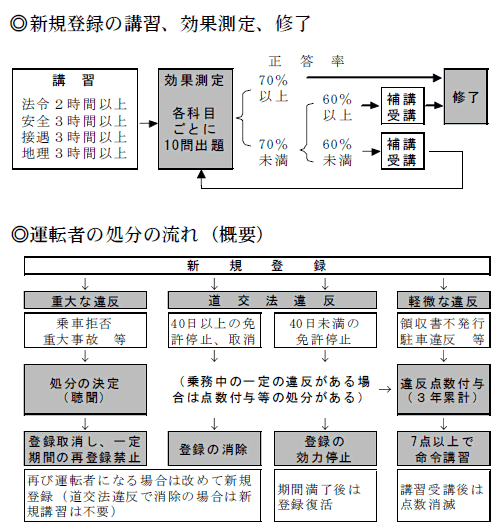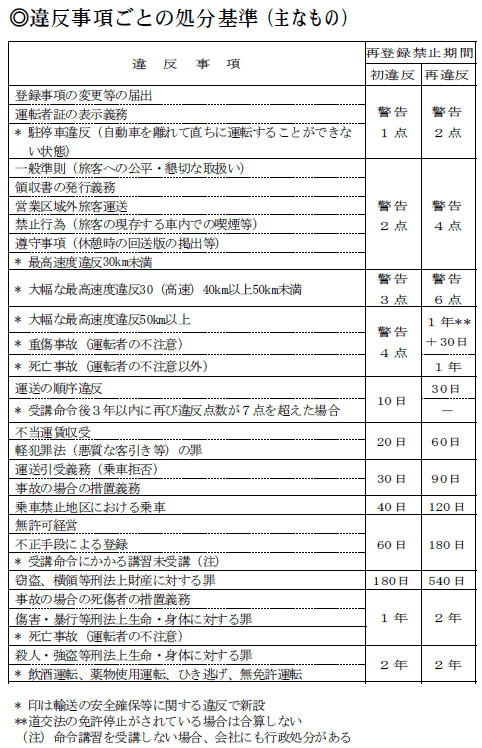|
|
 |
| 春闘の早期決着などを討議した第5回常執=6月11〜12日、自交共済事務所 |
議題は、(1)08春闘の中間総括骨子、(2)08年度運動方針骨子、(3)会計報告と、(4)次年度の予算案大綱、(5)役員体制・本部機構検討委員会の報告などでした。
春闘は、6月5日現在で、要求提出が75・1%、回答引き出し率54・3%、妥結率25・9%の実情のもとでの総括討議となりました。妥結した単組・支部の特徴は、運賃改定が実施された地方と改定のない地方を含めて、新たな合理化攻撃を許さなかったこと。そして、最も重視した(ノースライドに)プラスアルファを取っていることです。今後、未解決職場は、この流れで早期決着をはかることを重視します。
10月の定期大会の運動方針案の策定にむけては、将来展望を見据えた人事配置をめざし、「(1)くらしと雇用・いのちの危機打開にむけて。(2)未来をかけ、歴史的な闘いの先頭に立って。(3)目線を地域に、悪政打破の課題と結合して」とした情勢の特徴と運動基調の議論をしました。
| この成果を全国に |
宮城・塩釜交通労組
労働組合が支えてくれたことが勝利
仙台地裁
会社の不当労働行為を認定
【宮城】仙台地裁は6月12日、塩釜交通労組の鈴木さんが2005年7月28日に会社から、組合脱退工作をうけたことに対する損害賠償を求めていた裁判で、会社に対し、鈴木さんに50万円を支払うよう命じました。
この事件は、2005年、組合の弱体化を目的に会社が鈴木さんに対し、組合からの脱退を執拗に勧誘し、職場内に現役組合員が一人しかいなく、心細い思いを抱いていることを十分承知しながら、さまざまな不利益を継続し、組合を脱退すればそのような不利益から解放されて、仕事が提供されることをほのめかすなど、団結権を不当に侵害したものでした。
判決では鈴木さんになされた脱退工作を厳しく断罪し、不当労働行為と認定。会社に対し、50万円の支払いを命じました。
今回の勝利判決をうけて鈴木さんは「今回の勝利は、私を支えてくださったみなさん全体の勝利であると考えています。労働組合が支えてくれたことが、団結の勝利であると考えます。労働者の権利をきちんと知り、労働組合に結集するならば、必ず道はひらけると確信します」とお礼を話しています。
タクシー参入規制等の立法措置の動きについて
2008年6月11日
自交総連中央執行委員長 飯沼 博
 |
| 飯沼委員長 |
自民党のタクシー・ハイヤー議員連盟は5月30日、タクシーの増車・新規参入を時限的に停止する議員立法を秋の臨時国会に提出する方針を申し合わせたと伝えられている。民主党も、緊急調整措置の要件緩和などの緊急提言を近く国交省に提出する予定とされ、法案提出も検討しているとされる。また、国民新党は3月に新規参入・増車を3年間停止する時限立法の法案をつくり、野党各党に共同提案を呼びかけている。
一方、全タク連は5月30日にひらいた総会で、再規制をめざして与野党への働きかけを強めることとし、各都道府県協会が地元議員へ働きかけることを呼びかけている。
 |
| タクシーの規制強化を訴える自交総連の仲間 |
こうした動きは、タクシー規制緩和(道路運送法改悪)以来進行した、需要を無視したタクシー車両の増大、タクシー労働者の労働条件の際限ない低下と安心・安全の崩壊など、タクシー事業の混乱がもはや猶予のできない段階に達していることを背景にしている。
また、労働者派遣など不安定雇用の拡大、食の安全、投機資金による物価高騰など、構造改革・規制緩和が国民生活のあらゆる面で安心・安全を脅かしていることに国民の疑問が拡大していることも影響しており、政治の流れを変え、実際に規制緩和政策を見直させる可能性がでてきたことも示している。
自交総連は、タクシー規制緩和が強行される以前からその危険性を指摘して警鐘を鳴らし続けてきたものとして、与野党を問わず立法措置をも含めた対策を採らざるを得ないという共通認識にまで至ってきたことを歓迎する。参入規制等の緊急的な立法措置は、それが実現できれば相当な効果を発揮するものであり、有効なものとして実現するよう国会の内外で議論がすすむことを望むものである。
ただし、検討されている緊急の措置は、現に多すぎるタクシーを減車させる上では不充分な点がある。将来にわたって根本的にタクシー問題を解決するためには、減車を実現する方策の検討とともに、タクシー運転免許の制定など自律的な需給調整機能につながる対策が必要であることは、従来から自交総連が指摘してきたところである。
自交総連は、交政審ワーキンググループでの審議の動向もみすえてタクシー運転免許の法制化をいっそう高く掲げるとともに、当面の緊急措置として減車を実現するために、立法措置を含め、国交省の緊急対策、地方自治体の条例策定、独禁法の適用除外、事業者の自主的な減車などあらゆる側面から全力をあげるものである。
以 上
新たなタクシー制度設計が必要
交政審第7回 ワーキンググループ
次期国会に改正法案提出へ
交通政策審議会ワーキンググループは、6月17日の第7回会合で、中間とりまとめ(7月3日)を前に事務当局が示した4つの論点について一通りの議論を終えました。
今後のとりくみについて言及した本田勝・自動車交通局長は、「改めてこれまでの議事録を読み返し、整理をしていきたい。その上で行政の考え方をまとめさせていただきたい。この夏以降は具体的な制度設計の議論をしなければならない。これを受けて次期通常国会には改正法案として提出させていただく」と述べました。
また、「緊急調整措置は使い勝手の悪い制度であったが、9月以降、大幅な供給過剰地域の対策をどうするか。これらの施策についても考えていかねばならない」としました。
この日の会合では、「問題事業者の退出促進方策」と「運転者の労働条件確保と資質向上」について意見交換。今村書記長は、「既成の枠組みを超えた新たなタクシーの制度設計を視野に入れての議論が必要」とし、タクシー運転免許の有効性やタクシーの将来像について発言しました。
全職場で要求前進を
埼玉地連
中央委に34人参加
 |
| 要求前進を意思統一した中央委員会=6月19日、川越市・野草庵 |
議題となった、08春闘中間集約と単組別学習会や交通共済の拡大、タクシー乗務員登録制度など、6月から10月のとりくみなどの課題を旺盛な討論を行い、すべての議案を満場一致で決定しました。
春闘未解決組合は、運賃改定後の増収がないが、全職場で要求を前進させ解決することを意思統一し、同時に、足切り5万円引き上げというスライド攻撃を闘うダイヤモンド交通労組、未払い賃金や解雇事件など不当労働行為と闘う八千代交通労組、三和交通労組=東京高裁での裁判闘争を埼玉地連として全面的な支援で完全勝利をめざすことを確認。組合員拡大で積極的運動を進めているみずほ昭和交通労組を激励しました。
われら自交総連
3万人めざして(1)
規制緩和でタクシーは大混乱
私たちの賃金や労働条件を改善するためには、会社や行政に私たちの要求を認めさせることが必要です。そのためには、同じ産業で働く仲間が団結し、数の力を最大限に発揮することです。そこで、未組織の仲間にも自交総連を紹介できるように、労働組合の意義やこれまでかちとった政策闘争などを紹介します。無理な競争のしわ寄せで労働条件は最悪に
まじめに働いているのに家族も養えず、食べていくことさえ難しい――タクシー労働者はいまや日雇い派遣などの労働者と並んでワーキングプアの代表になってしまいました。
これは仕方がないことなのでしょうか? いいえ、そんなことはありません。タクシーがこんな状況になってしまったのには、れっきとした原因があり、その最大のものは、2002年から実施された規制緩和です。
現場で働くタクシー労働者の意見を無視して強行された規制緩和のために、利用者は減少しているのに、タクシー台数は急増、1台当たりの売上げがどんどん下がりました。経営者は、競争のツケを労働者にしわ寄せし、累進歩合制度やリース制など、低営収でも利益が出る「合理化」に必死となりました。
その結果、タクシー労働者の賃金は、全国最低の沖縄で年収183万円(07年)となったのをはじめ、多くの地方で4人家族の生活保護基準より低くなり、最低賃金法違反が続出するありさまです。
少しでも営収を増やそうと長時間労働となり、乗客を奪い合うため、交通事故が増加、多すぎるタクシーが道をふさいで、無駄なCO2を大量に排出しています。
力を合わせて、政府の規制緩和政策やそのツケをまわす経営者と対抗しなければ、事態はますますひどくなるばかりです。