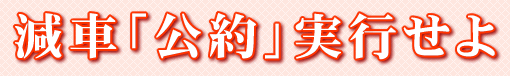|
|
 |
| 宣伝カーから訴える宮城地連の仲間 |
宣伝行動では、宣伝カーからの訴えと、本部作成チラシや宮城地連機関紙、ニュースを配布しました。
宣伝カーから、この間の減車のとりくみ状況や春闘の課題について訴えると、寒い中、車の外に出たり、窓をあけて聞いてくれたり、「早く減車をすすめてくれ」などの激励の声も寄せられました。また、この宣伝行動には、宮城県労連や交運共闘の仲間もかけつけました。
もっとタクシーを減らして
 |
| 宣伝カーから呼びかける福島地連の仲間 |
話をしてくれた乗務員からは、「確かに駅に待機するタクシーの台数が減ったような気がするが以前に比べて営収が上がった気がしない、もっとタクシーを減らして、利用者が増えなければ良くならない」と話し、また、駅前周辺に待機している乗務員さんからは、「この場所に3時間待機してやっとお客さんが乗ってくる。朝から夕方まで働いても売り上げが5000円なので、生活ができない」と嘆いていました。
運動で労働条件改善めざす
 |
| タクシーの実情を訴える東京北部の仲間 |
北部ブロックが担当する池袋駅西口宣伝には、東京地連の飯沼委員長、鈴木書記長が駆けつけ、飯沼委員長は「2002年2月1日に規制緩和政策の道路運送法が施行され、タクシーが増え始めタクシー乗務員の労働条件が悪化し始めました。それ以降、私たち自交総連は運動によって規制緩和から強化へ政策を変換させてきました。さらなる運動で労働条件改善をめざしましょう」と訴えました。
減車不十分で売上増加せず
 |
| 乗務員と対話する神奈川地本の行動参加者 |
運輸局前で座り込み宣伝
【大阪】大阪地連と京都地連は「怒りの行動」として、近畿運輸局前での座り込み宣伝を展開。220人(京都=19人、大阪=201人)の仲間が参加しました。
宣伝では、大阪地連の園田委員長が「大阪では第一次の減車計画が完了したが、特措法本来の趣旨である賃金改善は達成できていない。必要なのは(行政の)スピードと実態の検証だ」と強調。京都地連の森長委員長も「京都の減車率7・5%では不十分だ。賃金改善への道は実効性ある大幅減車と運賃の適正化しかない」と力を込めました。
最後に仲間はシュプレヒコールで「近畿運輸局は大幅減車に責任を果たせ!」「大阪労働局は累進歩合制賃金を根絶せよ!」と声をはりあげました。
 |
 |
| 「近運局は略奪運賃をやめさせろ!」と抗議の座り込みを行う大阪・京都両地連の仲間 | 夕方から独自で宣伝行動を行った京都地連の仲間 |
規制緩和の弊害を訴える
 |
| 乗務員にビラを渡す福岡地連の参加者 |
乗務員との対話では「タクシーが多すぎてお客さんを乗せられん、何とかしてもらわないかん」「駅の乗り場に並んで乗せるまでに3時間かかった」と景気の影響による利用者の減少と、タクシーの供給過剰が低賃金、長時間労働に拍車をかけていることが伺えました。
力を合わせ減車かちとろう
 |
| 乗務員にビラを渡し対話する鹿児島地連の仲間 |
【鹿児島】鹿児島地連は14人で、各駅や港などで待機中のタクシー乗務員に地連独自のチラシと本部作成のチラシ250枚をいっせいに配布し、「みんなで力を合わせて減車をかちとりましょう」と訴えました。
対話の中で聞こえてくるのは「タクシーが多すぎる、減車するべきだ」「事業者は何をしてるんだ」の声ばかりでした。また、ある乗務員は、「ほんとに車が多すぎる、しかし県タクシー協会の会長は減車どころかあっちこっちの会社を買収して自分の会社だけは車を増やしている。どうなってるんだ」などの声もありました。
「生活苦しい」が85%
はたらくみんなの要求アンケート
「はたらくみんなの要求アンケート」の集計結果がまとまりました。集計は、30地方1万0436枚、回収率53・1%となり、前年より4地方増え、回収枚数も2年連続で1万枚を超えました。
60歳以上が4割を超える
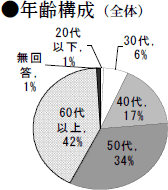 平均年齢は前年より0・3歳上がって55・6歳でした。年齢構成でみると、60歳以上が前年より3ポイント増えて42%となりました。
平均年齢は前年より0・3歳上がって55・6歳でした。年齢構成でみると、60歳以上が前年より3ポイント増えて42%となりました。
ハイタクに限った年齢構成では、60歳以上は、2000年には12%だったものが、昨年は39%、今年は42%に達しました。昨年やや増加した40歳代以下は、今年また減少に転じました。
生活実感圧倒的多数は苦しい
生活実感では「かなり苦しい」と「やや苦しい」を合わせると85%で前年(88%)よりやや減りましたが、圧倒的多数が苦しいことには変りありません。
高齢化が進行し、年金を受給しつつ勤務している人が増えたため、ゆとりがあると答えた人がわずかに増加したものと思われます。
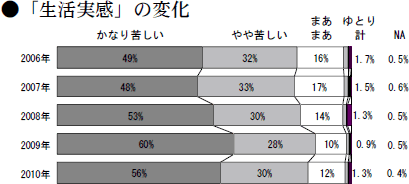
半数以上が貯蓄を取り崩し
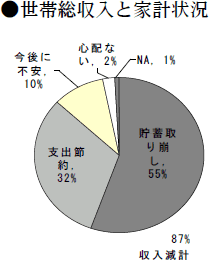 家族の分もあわせて世帯の総収入が減少しているのは87%です。前年が92%でしたから、わずかながら減っています。これも生活実感と同じく年金受給年齢に達した人が年金プラス賃金で前より増えたということが考えられます。
家族の分もあわせて世帯の総収入が減少しているのは87%です。前年が92%でしたから、わずかながら減っています。これも生活実感と同じく年金受給年齢に達した人が年金プラス賃金で前より増えたということが考えられます。
減少した家計収入への対応では、支出を節約したが32%、貯蓄を取り崩したが55%でした。節約だけでは追いつかずに貯蓄にも手をつけざるを得ない現状となっています。貯蓄取り崩しが5割を超えているのは3年連続変わっていません。このままでは貯蓄が底をつくのも時間の問題で、家計の破綻状態は深刻です。
賃上げ要求3万円以上は53%
3万円以上と答えた人が53%、平均要求額は3万5184円(前年3万8705円)でした。
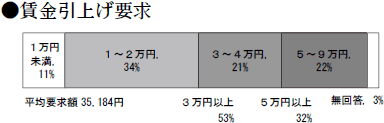
居眠り経験はタク34%、バス53%
労働時間について、長すぎて過労になっていると感じている人は79(前年64)%に達し、このままでは身体がもたないと感じる人が80(前年80)%、心の病になる不安がある人も71(同73)%にのぼりました。
ほとんどの人が長時間労働に不安、危険を感じているにもかかわらず、現実には賃金(売上げ)を増やすために長時間労働せざるを得ないという傾向が現れています。
また、タクシー、バス等の運転乗務員に限って、仕事で運転中の経験を聞いたところ、「よくある」「時々ある」を合わせて、交通事故を起こしそうになったことがあるがタク73%、バス71%、安全確認がおろそかになるがタク69%、バス65%、居眠り運転をしたことがあるがタク34%、バス53%に達しました。
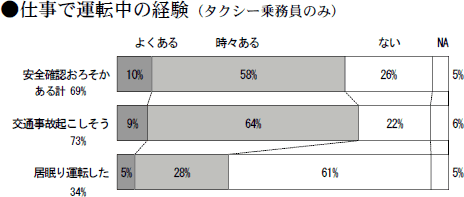
春闘要求では不満の把握が重要
政府に対する要求の上位3つは、(1)年金改善58%、(2)最賃引き上げ56%、(3)景気対策53%となりました。
また、職場での不満では1位が賃金が安いで75%、次いで有休が取れない33%、強盗等の不安26%でした。
地方ごとの違いをつかんで、自分の地方の不満をよく把握することが大切です。
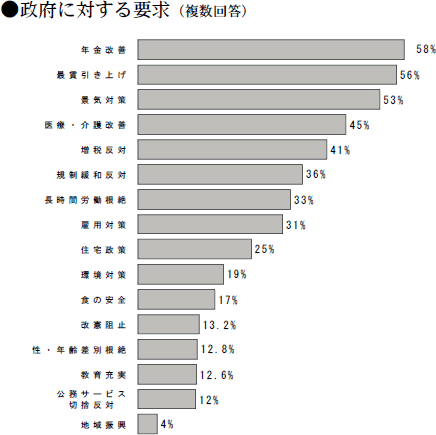
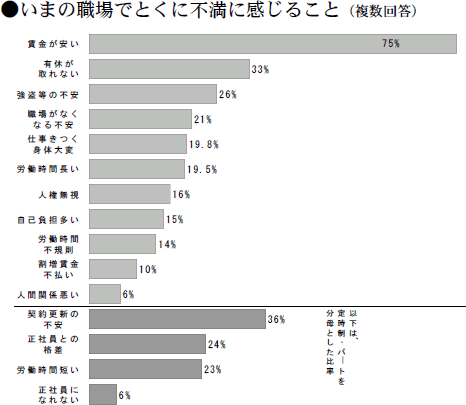
実効性ある交通基本法とせよ
「移動権」の考え方は大切
交運共闘国交省交渉
 |
| 申し入れ書を手渡す交運共闘・藤好議長=2月7日、国交省内 |
同省が通常国会に提出する準備をしている交通基本法案については、昨年末に検討小委員会がひらかれ、法案に「移動権」を規定することは時期尚早であるなどとする見解をまとめたため、法案が本来の法制定の意義を逸脱したものになるおそれが強まりました。
国交省が昨年6月に発表した「基本的な考え方」では、「交通基本法の根幹にすえるべきは『移動権』だと思います」と述べられており、その根幹を規定しないのでは、法の趣旨が生かされません。
交運共闘では、このような不適切な軌道修正をやめるとともに、交通機関の安全確保、それを担保する交通労働者の労働条件確保などの条項を入れるよう要請しました。
対応した総合政策局交通計画課山口課長は、条文上で権利と入らなくても移動権の考え方が大切だとの趣旨は生かしていきたいと回答しました。
交運共闘では、内容を薄めるのではなく実効性のある法案とするよう重ねて要請しました。
すべての労働者の賃上げを
丸の内から大手町へデモ行進
春闘闘争宣言行動
 |
| 横断幕を広げデモ行進する東京地連の仲間=1月14日、東京・丸の内 |
丸の内昼デモの出発式では、国民春闘共闘会議の小田川事務局長が「大企業の社会的責任を追及し、賃上げ、雇用拡大を柱とした2011年春闘に全力でとりくむ」と決意表明しました。
参加者は、丸の内仲通りから大手町の神田橋公園まで、「すべての労働者の賃上げ・雇用を実現しよう」と書かれた横断幕を広げ、シュプレヒコールをあげながら、デモ行進しました。
その後、日本経団連会館に移動し、包囲行動を展開。参加者全員が、経団連会館へむけて、「大企業は内部留保をはき出せ」「賃上げと雇用の確保を、中小下請けに仕事を」と力強く唱和し「団結がんばろう」で行動を締めくくりました。
| 新加盟のなかま | (797)東京・東日本キャブ労組 |
働きやすい職場めざす |
【東京】八王子市にある東日本キャブで働く仲間は昨年12月16日、自交総連東日本キャブ労組(八木龍一郎委員長、14人)を結成、自交総連に加盟しました。
会社では、一部職制による前近代的な労務管理などが行われていたため、改善に向けて話し合いを重ね、今回の組合結成、加盟となりました。
現在は、賃金・労働条件の改善と働きやすい職場づくりをめざして奮闘しています。