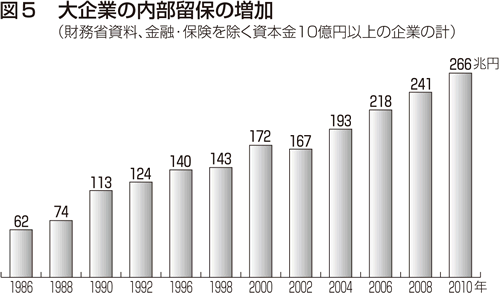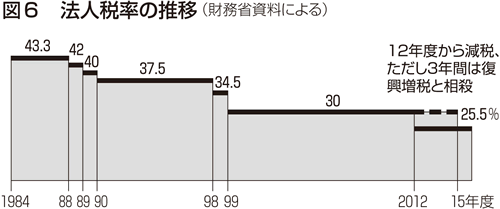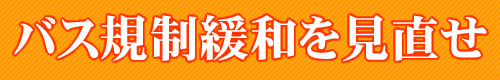|
|
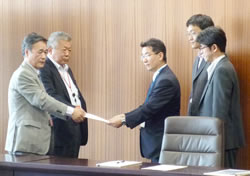 |
| 国交省に要請書を渡す藤好議長(左側手前)と飯沼委員長(奥)=5月18日、東京・国交省内 |
交運共闘藤好議長、飯沼委員長ら13人が参加、自動車局旅客課谷口バス対策室長ら3人が応対しました。
安全確保のための規制強化について、省側は「法令を守らない事業者が事故を起こしたことは、十分に安全を担保できてなかったということで、抜本的な見直しをしなければいけないと思っている。実効性が担保できるように、一から見直したい」と反省の弁を述べ、規制を見直すことを明らかにしました。
具体的に、▽交替運転者の配置基準は1日500キロ以下とすること▽深夜運行は、運転者2人制(ツーマン化)とすること▽「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を法制化し、内容を改善すること、を要請したのに対しては、「十分な労働条件を満たしていないという意見を頂戴している。配置指針や(労働時間の)基準そのものを含めて見直していく。5月中に検討会を設けて検討する」「夜間については、5月16日に国交大臣から、業界の自主的なとりくみとして夜間の長距離運行は2人運転とするように要望した」と回答。組合側は、検討会には自交総連の代表を入れるように要望、大阪の庭和田書記長が実情を述べ、規制は判りやすいものとする必要があると強調しました。
交渉には、建交労の乗合バスの仲間も参加、乗合も値下げ、労働条件の悪化がすすんでおり、全体の規制緩和を見直す必要があると訴えました。
労働条件確保こそが安全守る
穀田議員(共)が強調
衆議院国土交通委員会
 |
| 参考人に質問する穀田恵二議員(共)=5月18日、衆議院国土交通委員会 |
意見陳述では、関西大学の安部誠治教授が、(1)規制緩和で過当競争になり安全がおろそかになっている。事後監査では全部見きれない。参入規制の強化など見直しをするべきだ、(2)交替運転者配置基準の670キロは緩すぎる。総務省からも言われているのに直さなかった。見直すべきだ、(3)ツアーバスは乗合バスと比べて必要な費用負担をしていない。一本化するのはいいが、実効性を持たすべき、(4)旅行会社が優位な立場で低運賃を押しつけるなどの問題がある。旅行会社も規制できるしくみが必要だ――と述べ、事故の背景を指摘しました。
質疑では、日本共産党の穀田恵二議員が、自交総連の見解や5月12日に大阪地連バス部会の組合員から意見を聞いたことをふまえて、あずみ野観光バス事故の教訓が生かされず、総務省の勧告がなぜ実行されなかったのか、などの観点で質問、(1)参入資格の強化、(2)運転者の労働時間、賃金の最低基準の確保こそが安全を守る、(3)旅行業者の責任強化を求めました。
各党も規制緩和の問題点を指摘するなかで、みんなの党の柿沢未途議員は、今回の事故が規制緩和のためにおきたという証拠はない、安易に規制強化をすべきではない、などと異常な主張を展開しました。
24か所 718キロを走破
「仕事がない」と各地の声
鹿児島地連
 |
| ビラを配る鹿児島地連の仲間=5月15日、鹿児島・南埠頭 |
 |
| 乗務員と対話する宣伝隊=5月16日、鹿児島・指宿駅 |
創刊号発行したい
パソコン教室で意欲燃やす
東北ブロック教宣学校
 |
| 真剣な姿勢で実践にとりくむ参加者=5月15日、仙台市若林体育館 |
参加者は、パソコンでの機関紙作りは初めてという人がほとんどで、午前の部は編集ソフトの「パーソナル編集長」を使い、作り方の基本、イメージ枠の設定等を実践し、午後の部は簡単なビラを全員で作成し、3作品をみんなで講評しました。宮竹書記次長は「とりくむ姿勢が真剣で、短時間で作りあげた作品は上手」と講評しました。
参加した長谷部さん(福島・大和労組)は「いろいろなことが聞けて勉強になった」と話し、渡辺さん(宮城・仙南労組)は「近々創刊号を発行したい」と早くも意欲を燃やしていました。
みんなで決めみんなで行動
なら第34回大会
 |
| 組織拡大などの方針を決めたなら合同第34回定期大会=5月13日、奈良市内 |
林委員長は、組織拡大のためホームページを立ち上げ組織をグレードアップした、みんなで奮闘しようとよびかけ、小林議長が政治情勢にも触れ報告。みんなで決め、みんなで行動、500人組織の実現をめざそうなどの方針を確立しました。
議長=小林明吉▽委員長=林克己▽副委員長=小松譲二(新)、森本昌代、竹越修治▽書記長=小松秀之
未組織宣伝東北キャラバンの参加者の感想、2回目です
もう一度マイクを握りたい
山形・池田智行
 |
| 宣伝カー上でマイクを握る池田さん=4月11日、山形駅 |
私が同行した山形県と秋田県は自交総連の知名度の高くない地域です。2年位前までは自交総連など全く知らなかった秋田県のドライバーは、幸いに昨年、自交総連秋田地連が発足、横手タクシーが開業したことで、全自交労連以外のバス、タクシーの労働組合があることを知っていただいたことで、随分と宣伝行動がやりやすくなったと感じています。
乗務員の皆さんに共通して、労働条件の悪さ、特に賃金の低さについての声が圧倒的です。
わずか3日間ではありましたが、正直言ってかなり疲れました。しかし、普段、地元鶴岡でしか乗務していない私にとって、とても貴重な経験になりました。来年もう1回、今回参加できなかった東北4県でもマイクを握らせて頂ければと思っています。
職場権利の点検(7)
割増賃金には明確な区別が必要
残業(時間外)・深夜の割増賃金の支給方法で、「割増賃金を含めて歩合給○%」などという規定がありますが、これでは、賃金の中でどこまでが本体賃金で、どれが割増賃金か区別できないので、割増賃金を支払ったことになりません。
歩合給が○%、割増賃金が○%と、明確に区別されていなければなりません。この場合でも、下の計算のように、支払われた割増賃金が法定どおり計算された割増賃金より低い場合は、差額を支給しなければなりません。
形式的に割増賃金を支払ったことにして、それと同額を本給や調整給から引き去って相殺し、何時間残業していても、賃金総額は常に売上げ×○%になってしまうという賃金もしばしばみられます。
これでは法定労働時間を超えた労働への補償にならず、労基法の趣旨に反するものとして、違法であるとの判決が最近、札幌地裁で出されました。
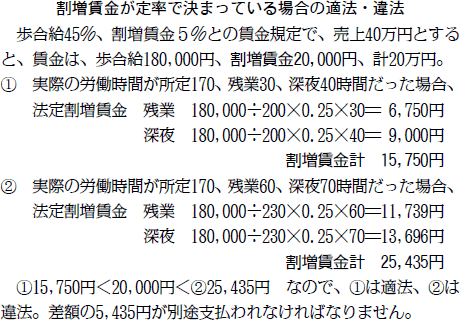
割増賃金が区別されないのは違法
【89・8・10 高知地裁昭62年ワ第666号】(歩合給に割増賃金を含める)支払方法が適法であるためには、歩合給の中のいくらが割増賃金に当たるかをそれ以外の賃金部分と明確に区別することができ、その割増賃金相当部分を控除した基礎賃金(これが通常時間の賃金に当たる。)によって計算した割増賃金の額と右割増賃金相当額とが比較対照できることが必要である。
割増賃金を相殺するものも違法
【11・7・25 札幌地裁平22年ワ第2320号】(被告の賃金規定は)時間外・深夜手当や歩合割増給を支給するものとはされているものの、結局その増額部分は被告の定めた算定方法の過程においてその効果を相殺される結果、原告らが時間外及び深夜の労働を行った場合において、そのことによって増額されるものではなく、場合によっては歩合給が減額することすらありうる。そうすると、その実質において法37条の趣旨を潜脱するものとして、その全体を通じて同条に違反する。
国民のくらしも国の財政も壊す消費増税
営収の大幅減、賃金減は必至
大企業・大金持ちに応分負担を
特集 消費増税阻止
増税は困るが、社会保障や国の財政破たんを避けるためにはやむを得ないのではないか――消費増税やむなしの論理がマスコミでもまことしやかに報道されています。本当はどうなのでしょうか。
限界超えた負担増
 |
| 消費増税ノー4・12集会=東京・日比谷野音 |
97年4月、消費税が3%から5%に上がりました。その結果は甚大なもので、当時わずかながら上向きかけていた景気は一気に急降下、深刻な不況に突入してしまいました。
タクシーの営業収入は、94年から96年までは増収が続いていましたが、97年には消費税分(初乗り10円)の値上げにも関わらず、かつてない乗客の乗り控えが起こって、99年までに14%も減ってしまいました。連動して運転者の年収は、消費税引上げ前の367万円が3年で16%減の307万円まで急落しました(図1)。
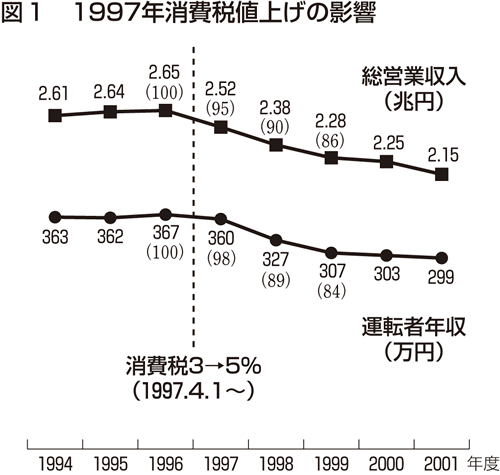
税控除でWパンチ
タクシー運転者の場合は、営収の減少に加えて、消費税を控除された上で賃金計算がされるので、さらに深刻な影響があります。
消費税は内税ですから、賃金計算をする場合には、今でも総営収から5%分の消費税を控除した税抜きの営収に対して歩率をかけて賃金を計算しているはずです。もし消費税が10%になったら、控除される額が倍になるということです。
仮に増税分を運賃に転嫁したとしても97年の時にみられるように営収が増える保障はまったくなく、逆に減ることが考えられます。月間営収50万円が1割下がったとすると、控除額は4万909円で、賃金は3万3550円も下がってしまいます(図2)。
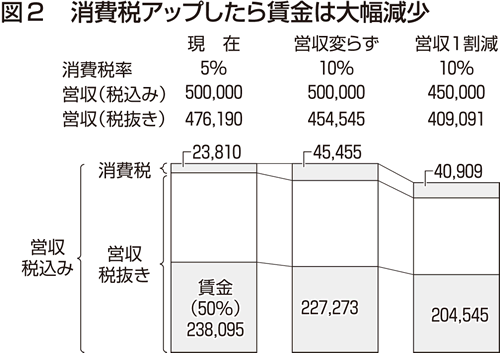
税収は逆に減少
それでも、財政再建のために必要だと政府は言いますが、消費増税は、財政再建に役立ちません。
景気が悪化し、国の税収にも影響するからで、97年の消費税引き上げ後の実績をみればわかります。96年度に90兆円だった税収はいまでは76兆円、結局は、消費税の増収をすべて帳消しにする減収になっているのが実態です(図3)。
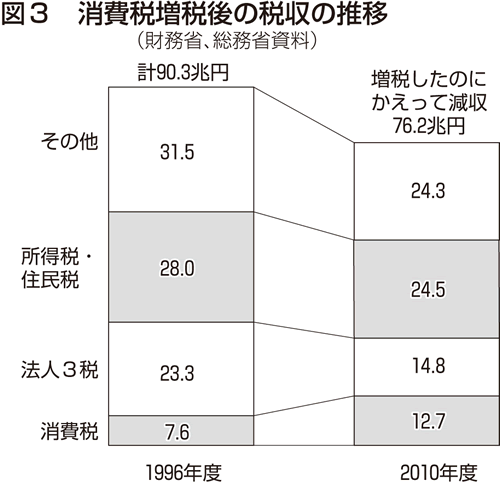
大企業・大金持ちに応分の負担を
それでは、どうしたらいいのか――税金は負担能力に合わせて、大企業や大金持ちに応分の負担をしてもらうのが原則。それをきちんと行えば消費増税は必要ないはずです。
図4にみるように、現在の所得課税は、年収1億円を超えると逆に負担率が下がっていきます。大金持ちの収入源である株や証券への課税が分離課税10%と優遇されているからです。預金利子にも20%課税されるというのに、株の利益は何億、何兆円でも10%しか課税されません。
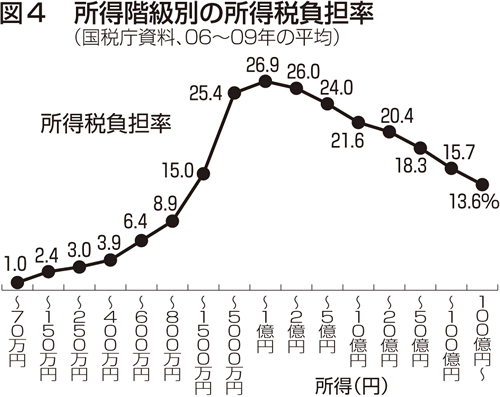
また、大企業は内部留保を増やし続け、10年度には266兆円にも達しています(図5)。金余りで投機資金などに流入しているのに、法人税は減税が繰り返され、15年度からはさらに4・5%減税することが決まっています(図6)。